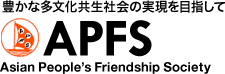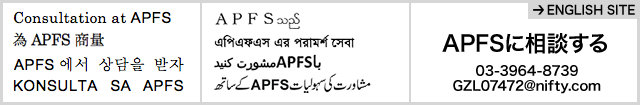11月26日に日本社会事業大学ヴイラーグ・ヴィクトル准教授を講師にお招きし、第5回相談員育成講座「多文化ソーシャルワーク」を開催しました。
初めに対人援助専門職としてのソーシャルワークの概念と特徴について、要支援者を困った人ではなく環境と合わないだけの人ととらえ、ソーシャルワーカーには人々に働きかけ、取り巻く環境に働きかけ、さらに人々と環境の関係や接点に働きかける視点が必要との話がありました。続いて文化の多様性に対応できるソーシャルワークの基本として、支援者には文化の異なる集団のニーズを満たし、効率的に支援できる実践力が求められていることがわかりました。さらに相談員として求められている面接技術の基礎や、構造的な差別に立ち向かう必要性について教えていただきました。特に、真の地域共生社会・多文化共生社会を考える・作るうえで「我が国」の「我」が誰を指すのか、どこまで包摂するのか再考する必要があるという最後のメッセージが心に残りました。日ごろ相談活動している方々に新たな視点で活動を振り返るヒントが得られたと思います。(報告:ボランティアスタッフ阿部秀樹)
*この講座は「パルシステム東京市民活動助成基金」の助成を受けて実施しています